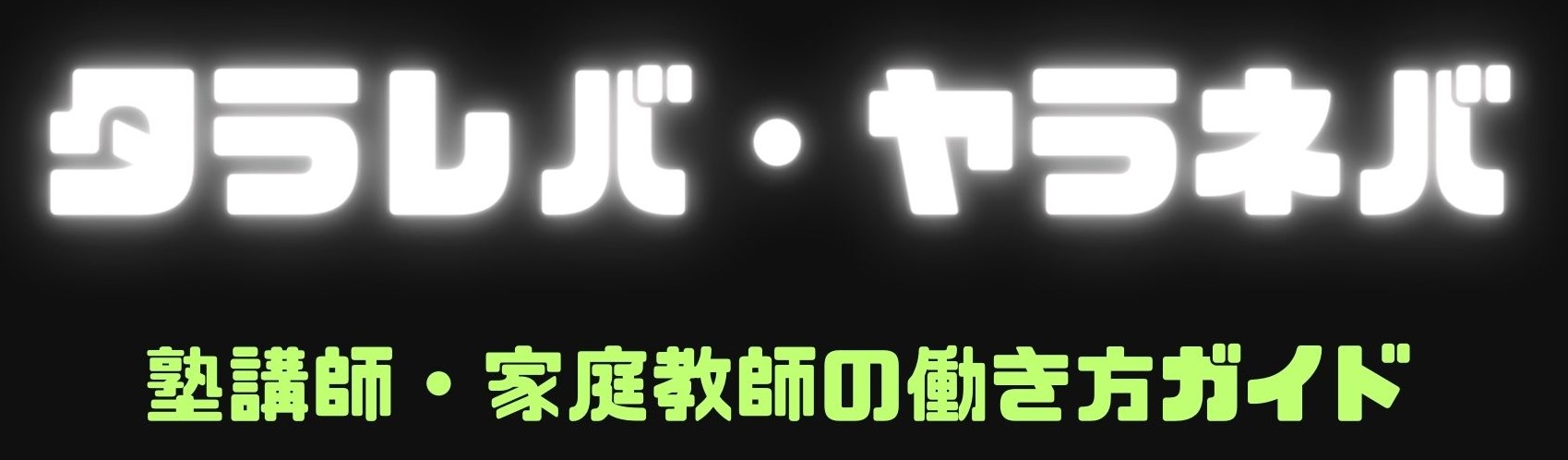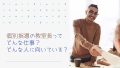こんにちは、プロ講師のひかるです。

そもそも模擬授業って何?
何をすればいいんだろう…
塾講師になろうと考えているかたで、そのように悩んでいるかたも多いのではないでしょうか?
講師の仕事をまだ経験したことがないかたにとっては、模擬授業ってイメージが湧かないですよね。
今回の記事では…
がわかります。
- 塾講師として転職したい人
- 塾講師のアルバイトがしたい人
におすすめの記事です。
しっかりと準備をして、模擬授業の選考に挑んでくださいね!

元塾講師・プロ家庭教師の私が解説します!
塾講師の模擬授業ってどんなもの?

塾講師にとっての模擬授業とは…
実際の授業を想定したシミュレーション用の授業
です。
塾講師になるための選考の一部として、模擬授業をさせる会社があります。
また、採用が決まってからも、研修として模擬授業を行うことも多いんです。
技術を磨くために、定期的に模擬授業の研修をおこなう会社もたくさんありますね。
今回の記事では、塾講師になるために初めて模擬授業をする人向けに、模擬授業のノウハウをお伝えしていきます!
模擬授業の形式
模擬授業はどんな形でおこなうのでしょうか?
基本的には、採用担当者(面接官)を相手に、授業をおこないます。
模擬授業の形は、集団指導と個別指導で大きく違ってきます。
- 【集団指導】黒板(ホワイトボード)を使って授業する
- 【個別指導】生徒役の隣に座って授業する
生徒役の採用担当者を相手に、1つの単元や問題を解説するパターンが多いでしょう。
模擬授業の流れ
次に、模擬授業がどのように進んでいくのか見ていきましょう。
模擬授業による選考は、大きく3つの流れがあります。
- 単元・問題を事前に指定される
- 単元・問題を自由に決めてOK
- 単元・問題は当日指定される
という3つです。
事前に単元・問題を指定されたり、自由に決めていい場合には、じっくりとプランを練って模擬授業に臨めます。
でも、単元・問題を模擬授業の当日に指定されると、焦りますよね…
まず、問題を解けないといけないですし、授業の構成もその場で考えなければなりません。

採用試験として私は2回模擬授業をしましたが、2回ともフリーテーマで助かりました
さきほど紹介した通り、採用担当者を相手に、模擬授業をおこないます。
模擬授業自体は、10~20分くらいで終わります。
切りのいいところまでパフォーマンスできるときもあれば、面接官が途中で打ち切るときもあるでしょう。
模擬授業の後に、選考の担当者から、コメントやアドバイスをもらえることがよくあります。
模擬授業の5つのテクニック

模擬授業は、あくまでシミュレーション用の授業です。
でも、シミュレーション用の授業だからこそ工夫すれば、良いパフォーマンスを見せることができます。
ここからは、主に集団指導の模擬授業、つまり、黒板(ホワイトボード)を使った模擬授業のテクニックを紹介していきます。

個別指導の模擬授業について知りたい方は、黒板の使い方などは読み飛ばしてくださいね
模擬授業の5つのテクニックは…
- 授業の展開
- 板書のクオリティー
- 生徒役(採用担当者)への問いかけ
- 言葉づかい・ふるまい
- レベル設定に合わせたテンポ
です。
1つ1つ見ていきましょう。
授業の展開
まず、どのように授業を進めるかという「授業の展開」に注目してみましょう。
たとえば、歴史の授業で「平安時代は、桓武天皇が京都に都を移してスタートしました」と、いきなり本編から話し始めても、もちろん悪くはありません。
ただ、漫才と同じように、聞く人を引き付ける「つかみ」があると良いですよね。

ミルクボーイの「ベルマークをいただきましたけどもね。こんなんなんぼあってもいいですからね」ってやつやな
もちろん本物の漫才のように、笑うを取る必要はありません。
授業の進め方としておすすめなのが…
などでしょう。
少し掘り下げて見ておきましょう。
知っていることから新しいことへ
いきなり新しいことから話し始めると、聞き手がついてこられないときがあります。
まずは、知っていることから話し始めて、じょじょに新しい内容に展開すると、理解しやすくなります。
たとえば、さきほどの平安時代の例なら…
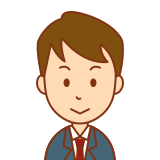
奈良時代は仏教の力が強かったよね。
お坊さんに政治に口出しされたくない天皇は、都を別の場所に移したんだ。
というように、前回までに習った内容と関連付けると、授業の入りがスムーズになります。
また、「そうだった」と前回の内容を軽く復習することで、記憶にも残りやすくなります。
「既知から未知へ」というのは、相手に伝えるテクニックの1つです。
単元全体を見渡せる授業
また、単元全体まで視野を広げておくと、わかりやすい場合もあります。
先の平安時代の例なら、こんな感じ↓
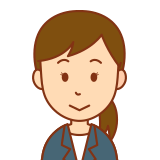
平安時代は400年くらい続くよ。
だから権力者がけっこう変わります。
天皇、貴族、上皇、武士って感じ。
先に、全体像を把握したほうが、「今、自分が何を学んでいるのか」がわかりやすいですよね。
まずは、頭に中に、単元という「ひきだし」を作ってあげる。
その大きな箱の中に、新たに教える小さな知識を整理して入れていくイメージです。
さきほどの「既知から未知へ」と組み合わせて使っても、効果的でしょう。
先に具体的に理解させる
抽象的な話からスタートすると、伝わりにくいことがあります。
特に、小学生や中学生に話すときには、具体的な例をあげた方が伝わりやすくなります。
たとえば、「平均」の授業をするときに…
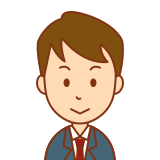
「平均」っていうのは、「全体を平らにした数」で、「合計÷個数」で出せるよ
と説明しても、子どもたちの頭には「?」が浮かんでしまうでしょう。
それよりも具体例を出してあげた方が、腑に落ちます。
さきほどの平均の授業の例なら…
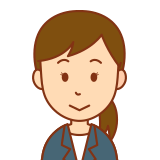
A君が1000ml、B君が600mlのジュースを持っているとするね。
A君がB君に200mlあげたら800mlで同じになるでしょ。
こうやって数字を「ならす」ことを「平均」というの。
という感じですね。
このあと、(1000+600)÷2=800という計算方法を教えたり、「では、3人の場合はどうなると思う?」と展開したりするといいでしょう。
中には、細かい理屈を説明するよりも、概念や公式を覚えさせた方が早い場合もあります。
どうやって授業を展開すれば、子どもたちが理解しやすいのか、のちのち研究していきましょう。
板書のクオリティー
テクニックの2つ目は、黒板(ホワイトボード)の使い方です。
板書の使い方で、「あ、この人、授業に慣れてるなor慣れていないな」というのが、よくわかります。
※個別指導の講師を目指していて、板書が必要ないかたは読み飛ばしてくださいね。
板書のテクニックは…
などです。
もう少し掘り下げて見ておきましょう。
板書のレイアウト
まず、黒板(ホワイトボード)のサイズを上手に利用しましょう。
大きな黒板なら、左と右で2分割して、左から書き進めるといいでしょう。
慣れていないと、黒板のど真ん中から書き始めてしまう人も…

国語は、右から縦書きやな
小さなホワイトボードの場合は、分割する必要はありません。
それでも、「伝えたい内容が板書でどうおさまるか」をイメージしておきましょう。
慣れるまでは、ノートや紙に板書の下書きをしておくのをおすすめします。

私も、塾講師時代はめちゃくちゃ下書きして、美しい板書を目指しました
また、黒板の方を向いて書くと、書いている文字が体で隠れてしまいます。
生徒に背を向けず、体を開きながら、板書できると慣れている感じが出せます。
字がていねい
また、ある程度の字のていねいさも必要です。
書き殴ったような板書をする講師もいます。
でも、なんだかんだで、授業がわかりやすい先生って、字も(ある程度)きれいなんですよね。

予備校の先生のクセ字に憧れて、マネしてたわ
子どもたちに理解させるのは、話す言葉だけではありません。
黒板(ホワイトボード)に文字や絵をかいて、視覚に訴えかける。
わかりやすい板書によって、知識が子どもたちの記憶に残りやすくなるのも事実です。
- 算数(数学)…図形・線分図
- 社会…地図
- 理科…実験器具や動植物のイラスト
このような教科特有の内容を、テキストなどを見ずにすらすら書けると、採用担当者にも「おっ!やるな」と思ってもらえます。
板書が美しいだけで、子どもたちも一目置いてくれますよ。

ホワイトボードって、まっすぐ線を引くのが意外と難しいんです
色の優先順位が決まっている
チョーク(ホワイトボードマーカー)の色の優先順位を決めておくといいでしょう。
統一しておかないと、どこが重要なのかが伝わりにくくなってしまいます。
黒板の場合は…
- 赤
- 黄色
- 白
という優先順位が、一般的ですね。
1番強調したいことは赤、2番目は黄色、それ以外は白で書くということです。
一方、ホワイトボードの場合には…
- 赤
- 青
- 黒
という優先順位が多いでしょう。
ただし、算数(数学)で複雑な図形を描く場合には、黒で元の図形をかくと、あとで上から別の図形を重ね書きしにくくなります。
ですので、元の図形を、緑やオレンジなどの薄めの色でかいておき、黒・青などの濃い目の色で重ね書きをする講師もいます。
また、オンライン授業の場合には、ホワイトボード上の黒と青の見分けがつきにくい場合があります。
オンラインでは「青ではなく緑を使う」など、ルールを決めておくといいでしょう。

歴史の授業では、人物名は赤、それ以外の重要語句は青(黄色)と私は決めています
生徒役(採用担当者)への問いかけ
録画されている映像授業と、実際の授業との違いはなんでしょうか?
それは、対面の授業では講師と子どもたちとのコミュニケーションが起こることですよね。
一方的な話を聞き続けるよりも、「参加型」の授業の方が理解が深まると言われています。

いつ名前を呼ばれるかわからんから、気が抜かれへんもんな
ですので、集団指導であれ、個別指導であれ、子どもたちに「問いかけ」をする。
そして、子どもたちの反応に見ながら、授業を進めていきます。
模擬授業でも、生徒役の採用担当者に「問いかけ」をしてみましょう。
採用担当者が「鈴木」という人なら、遠慮せずに「鈴木さん」と名前を呼びます。
「問いかけ」のポイントは、単元のキーワードや子どもたちに考えさせる問いかけをすることです。
たとえば…
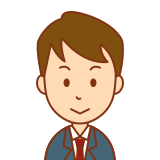
【単元のキーワード】
佐々木くん、球の体積の公式は何だった?
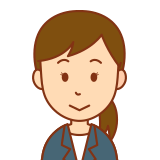
【考えさせる問いかけ】
田中さんは、藤原氏がどうすれば権力を握れると思う?
などです。
一方的に話し続けるのは避けましょう。
講師が問いかけ、子どもたちが答えることによって、いっしょに授業を進めると考えるとイメージしやすいかもしれません。
音楽のライブでも「コール&レスポンス」があると、盛り上がりますよね。
言葉づかい・ふるまい
言葉づかい・ふるまいが、採用担当者に見られるのは面接と同じです。
ただ、模擬授業では、次のことにも気を付けるといいでしょう。
などです。
生徒役の採用担当者と、視線を合わせるようにしましょう。

緊張するやんけ…
緊張すると、ついつい早口になってしまう人も多いでしょう。
あえていつもよりもゆっくり話すのがおすすめです。
また、緊張すると、表情がかたくなってしまう人も多いもの…
無理のない程度に、にこやかに授業できるといいですね。
身振り手振り(ジェスチャー)を交えると、表情豊かな授業を演出できます。

子どもたちを引っ張っていくパワーはあるかな?
子どもたちを引っ張って授業をするのは、エネルギーが要ります。
採用担当者も、模擬授業から講師の熱量が感じられるか見ています。
(自分のキャラクターにもよりますが)淡々とせず、明るく元気に模擬授業ができるといいですね。
レベル設定に合わせたテンポ
今度は、少し高度な内容になります。
まれに模擬授業のレベルを設定されることがあります。
たとえば…
- 苦手な子に向けた英語の授業
- 最難関向けの数学の授業
といった感じです。
レベルが設定されているときには、その水準に合わせた模擬授業をする必要があります。
英語が苦手な子がつまずかないように授業しなければなりません。
数学が得意な子が、退屈しないようなスピーディな授業が求められます。

講師の職を未経験のかたに、レベルまで要求されることはあまりないはず
特にレベル設定がない場合には、「苦手な子でも理解できるテンポ」を心がけるといいでしょう。
まとめ:塾講師になるための「模擬授業」5つのテクニック
塾講師にたるための選考の1つである、模擬授業のテクニックを紹介してきました。
採用担当者に…
- どんなところを見られているのか
- どう見せるのか
を知っておくことで、良いパフォーマンスを見せることができるでしょう。
模擬授業でベストを尽くせるよう、応援しています!