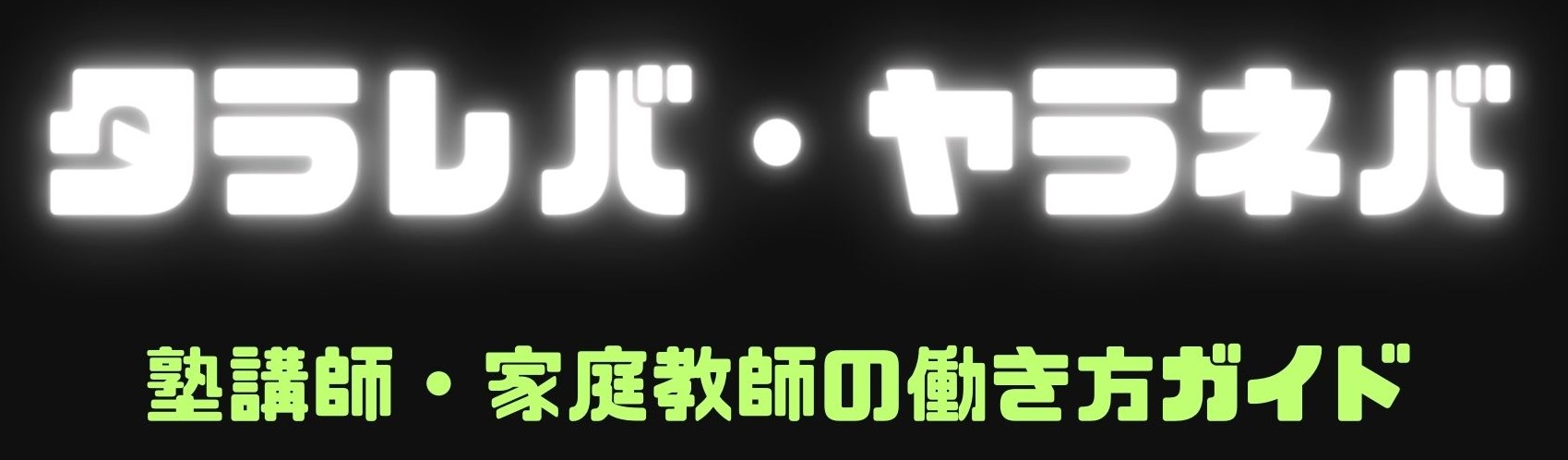こんにちは、プロ講師のひかるです。

塾講師って離職率が高いって聞くけど、ほんと?
辞めたくなるような仕事なの?
塾業界に興味があるけど、塾講師の離職率が心配な方も多いのではないでしょうか?
今回の記事では…
がわかります。
- 塾講師として就職・転職したい
- 塾業界に就職したけど将来が心配
そのような方の参考になれば幸いです!
特別な資格も必要のないオープンな仕事ですが、離職率が高い原因を探ります。

元塾講師が解説します
塾業界・塾講師の離職率は?

まず、塾業界の離職率がどれくらいなのか見ておきましょう。
厚生労働省の平成29年度の統計によると…
新規学卒就職者の産業別就職後3年以内離職率のうち離職率の高い上位5産業(大学卒業)
厚生労働省「新規学卒就職者の離職状況(平成29年3月卒業者の状況)」
宿泊業・飲食サービス業 52.6% 生活関連サービス業・娯楽業 46.2% 教育・学習支援業 45.6% 小売業 39.3% 医療、福祉 38.4%
となっており、離職率の高い業界として3番目に「教育・学習支援業」が挙がっています。
「教育・学習支援業」には、いわゆる「塾」以外の業態が含まれているとは思います。
ただ、それでも塾をはじめとする教育業界の離職率が高いのは気になりますよね…
実際、私も10年間正社員として勤めた塾を退職しました。
私の先輩や同僚、知り合いの塾講師の多くが、勤めていた会社を辞めています。
(会社を辞めたいor退職した理由はこちらの記事をどうぞ↓)
私は現在プロ家庭教師として担当しているご家庭からも、「通っている塾の講師がころころ変わる」という話はよく聞きます。
塾講師には特に決まった資格が必要なわけではありません。
塾講師になろうと思えば、基本的にだれでも塾講師になることができます。

だからこそ四谷大塚の件のように、塾講師に本来なってはいけないような人が入社してしまいます…
それなにの、どうして塾業界では離職率が高いのか、その理由を見ていきましょう。
※塾講師として就職・転職したいかた向けのまとめ記事はこちらです↓
塾講師の離職率が高い理由6つ

塾講師の離職率が高い理由は…
- 勤務時間外の仕事が多い
- 休みがとりにくい
- 入試直前期には休みがない
- かと言って給料が高いわけでもない
- 授業に専念できなくなる
- 入社したときの理想とギャップが大きい
の6つです。
1つずつ掘り下げて見ていきましょう。
※塾講師の転職についてのまとめ記事はこちらです↓
勤務時間外の仕事が多い
新卒で塾業界に就職すると、まず「勉強」が必要になります。

勉強が得意やから塾講師になったんちゃうん?
と、思われるかもしれませんが、自分自身が解けるのと、子どもたちを「解けるようにする」のは別の話です。
テキストの問題をひと通り解いておく必要がありますし、黒板(ホワイトボード)の使い方を計画しておかなければなりません。
教え方がいくつかある場合、どの教え方がベターなのかを考えなければなりません。

教え方は、塾によっても、子どもたちの学力によっても違ってきます
そのような授業の準備を、勤務時間中に済ますことができれば問題ありません。
でも、昼間に授業の準備ができないことは多いです。
- 研修
- 会議
- 保護者懇談
- 電話対応
- 来客対応
- チラシ配り(営業)
など、授業以外にもいろいろな業務が実はあります。
ほとんどの塾が13:00~22:00といった勤務形態ですが、残業したり、早く出社したり、テキストを持ち帰って家で準備をするようになります。
授業に慣れて、教科の知識や板書のプランが頭に入っているベテランになると、楽になるのでしょうか?
実はベテラン塾講師になっても、予習や準備は必要です。
新しい年度の入試問題を解いたり、常に情報をアップデートしておく必要があります。

人気の看板講師やトップ講師ほど、実はめっちゃ研究していますよ
休みがとりにくい
タスクは早めに終わらせて、1日有給休暇を取る。
塾講師の授業は、そういうタイプの業務ではありません。
週単位で時間割が決まっているので、休みにくいです。
体調が悪かったとしても、子どもたちが都合よく休んでくれるわけではありません。

他の講師に代講を頼めばええやん
そう思われるかもしれませんが、代講をお願いするのは気が引けるものです。
他の講師たちも、夕方以降に授業がびっしり埋まっているのに、なかなか代講が見つからないということもあります。
公休の社員にわざわざ出勤してもらわなければならないこともあります。

結婚式と新婚旅行のときには、他の教室からヘルプに来てもらいました…
休みがとりにくい勤務形態なので、有給休暇は消化できないまま、という社員が多いでしょう。
また、上場していない会社では、産休・育休・介護休などのシステムが整っていない塾も多いでしょう。
大企業であっても、女性講師が少ないのが現状です。
入試直前期には休みがない
入試が近づいてくると、そもそも休みがなくなる塾が多いです。
ほとんどの場合、冬期講習(12月)くらいから忙しくなり、年末年始の休みを最後に、怒涛の連勤がスタートします。
また、入試前の追い込み授業に並行して、新年度の募集もスタートしています。
たとえば、高校受験の塾ならば…
- 新中1(現小6)
- 新中2(現中1)
- 新中3(現中2)
- 受験生(現中3)
という4学年の中学生クラスが存在するという状態になります。
中学受験や大学受験も同様ですね。
受験シーズンに突入すると…

おれ、年明け20連勤やわー
みたいな「連勤自慢」が始まる職場は要注意です。
※塾講師が転職するときの流れ・注意点について詳しくは、こちらの記事もどうぞ↓
かと言って給料が高いわけでもない
時間外の業務が多かったり、休みにくかったりするのも、離職率が高い原因だとは思います。
でも、それで給料が高かったら、ガマンして働ける人も多いでしょう。
ということはやはり、「給料がそれほど高くはない」ということが、離職率が高い要因の1つになっているはずです。
求人ボックスというサイトが、政府統計をまとめた情報によると、塾講師の平均年収は…
376万円
求人ボックス 給料ナビより引用(2023年10月31日)
となっています。
もちろんある程度は年功給ですし、役職がつけば年収は500万円を超えます。
大手の塾会社で昇進していけば、1,000万円前後の年収まで昇給することはあり得ます。
でも、中小規模の塾では、それほどの年収は見込めなかったり、大手の会社に勤めていても、昇給する前に離職する人が多いのが現状です。
より高い年収が得られる塾に転職したり、別の業界に転職したりする人が多いです。
授業に専念できなくなる
さきほど、役職がつけば年収も上がっていく、と書きました。
ただ、役職がつけば、授業以外の業務がだんだんと増えていきます。
たとえば、教室長はいわゆる「中間管理職」的な存在です。
中小規模の塾であれば上には幹部がいますし、大企業であれば上にエリア長などが存在します。
一方で、教室の社員や非常勤などのスタッフを育てなければなりません。
すると…
火曜日:エリア会議
木曜日:運営会議
というように、役職に付随する会議や仕事が増えてきます。
かといって、教室長自身が担当する授業が大幅に減るというわけではありません。
「プレイングマネジャー」として、自分も授業をし続けなければなりません。

代打オレじゃなくて、俺レギュラーなんかい
私自身は塾講師時代に国語科の統括をしましたが、やはり会議やプロジェクトは多くなりました。
塾講師は、自分の授業にこだわりを持った人が多いですから、本来は授業に専念したいという職人気質の人はストレスが溜まってきます。
その結果、授業が上手な講師が離職してしまうという、もったいない離職が起こってしまいます。

塾講師はよく言えば個性的、悪く言えば、クセがすごい!
※塾講師におすすめの転職エージェントについてまとめた記事はこちらです↓
入社したときの理想とギャップが大きい
時間外の業務が多くても、また、休みがとりにくくても、入社するときにある程度わかっていれば、離職が防げるかもしれません。
入社したときの理想と、塾講師の現実のギャップが大きいのが、離職率を高める理由の1つになっているのではないでしょうか?
転職組の講師で、転職先で勤め続ける人がいます。
そういう転職した塾講師たちは…

前の会社に比べたら、今の会社はまともやでぇ
ということが多いです。
つまり、塾業界の現実を知っている人は、新しい職場で不満があったとしても、やっていけるという側面もあるということです。
そうならないためにも、特に新卒で塾業界に就職する場合には、塾業界の労働環境を事前に知っておくといいでしょう。
もちろん「時間外の業務が多い」とか「有給・産休・育休を取りにくい」といった環境は、改善されていかなければなりませんね。

まとめ:塾業界の離職率が高い理由
ここまで塾講師の離職率が高い理由を紹介してきました。
塾業界は「ブラック」と言われることがよくあります。
でも、本来は、子どもたちの成長を見届ける、とてもやりがいのある仕事です。
熱心な講師たちが離職につながるような労働環境や条件は、早く解消してもらいたいものですよね。
保護者といっしょに、子どもたちを教える、熱心な塾講師たちのためにも…
私自身は体調を崩して離職し、現在はプロ家庭教師として独立・開業しています。
拙著『プロ家庭教師として生きていく方法』でも、塾業界・受験業界の労働環境について触れています。
離職後に独立・開業をお考えの方は、ぜひご覧ください↓
お持ちのスマホ・タブレットのkindleアプリでお読みいただけます。